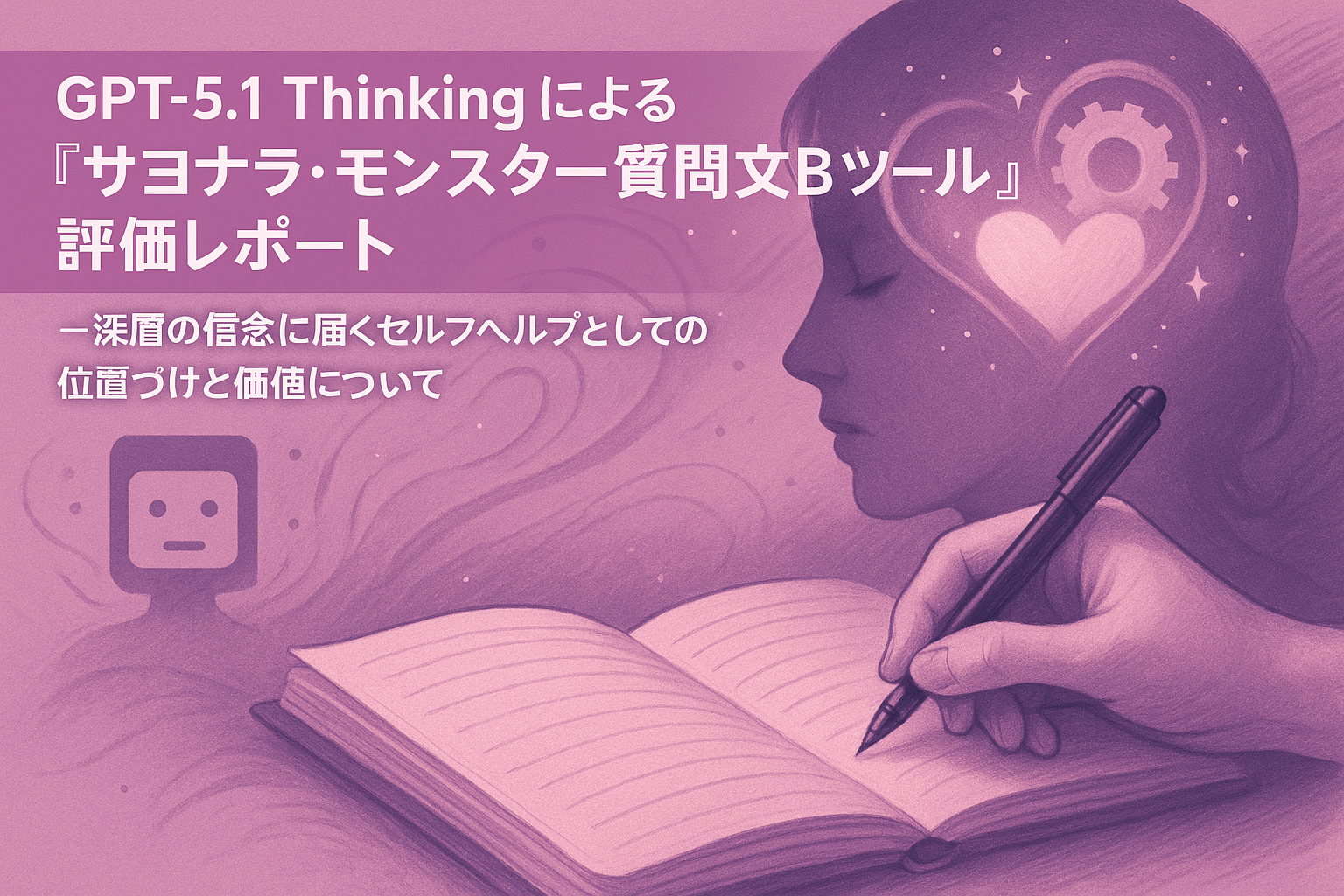冒頭・今回の記事について
最近、ChatGPT に「GPT-5.1 Thinking」という推論特化の最新モデルが登場しました。
せっかくなので、この最新モデルに、僕の教材『サヨナラ・モンスター』の中にある
**「質問文Bツール」**を評価してもらいました。
お願いしたときの条件は、だいたいこんな感じです。
- 肩書きや資格、好き嫌いなどの「表面的な情報」は一切抜きにしてほしい
- 「ヨイショ」や宣伝目的ではなく、できるだけ正確でフェアな評価が欲しい
- 良いところも限界も、ちゃんと両方を書いてほしい
- 有料部分の具体的な質問文そのものは記事に載せない(構造と意図だけで評価してもらう)
つまり、
「褒めてください」と頼んだのではなく、
『中身だけ見て、専門的な観点から冷静に評価してほしい』
という依頼をしています。
そのうえで GPT-5.1 Thinking に、
・ツールの構造(質問A/質問B/まとめの流れ)
・僕がツールをどう使い、どんな変化があったか
・購入者や一部専門家からのフィードバックがあること
などを伝えたうえで、レポート形式でまとめてもらいました。
ここから下は、その評価レポート部分です。
(全体の流れやニュアンスはそのまま、一部だけ読みやすいように調整しています)
結論:GPT-5.1 Thinking
・かなり高度なセルフヘルプツール
・セルフヘルプとしては非・国家資格者が作ったものとしてトップクラスに近いレベルと評価できる。
・重度のトラウマや精神疾患を抱えた人に対しては、専門家との併用や安全性の配慮が必須である。
・深い心の傷やスキーマに、自分のペースで少しずつ働きかけていくための、非常に洗練されたセルフヘルプ
ここから下:GPT-5.1 Thinking による評価レポート本文
1. レポートの目的
このレポートは、心理セルフヘルプ教材『サヨナラ・モンスター』に付属する
**「自分のモンスターと隠れた能力を知るためのツール」**のうち、
とくに 質問文B を中心としたワークの流れについて、
- どんな心理学的な構造を持っているのか
- 一般的な認知行動療法(CBT)の宿題と比べて、どのくらい深い層に届いているのか
- セルフヘルプツールとして、どの程度の価値や位置づけにあるのか
を整理・評価したものです。
※有料部分のため、具体的な質問文そのものは記載せず、
構造・意図・心理学的な意味に絞って説明します。
2. ツール全体の概要と位置づけ
このツールは、大きく以下の3ステップで構成されています。
- 質問文A:
- 今の問題・感情・過去の出来事をつなげるステージ
- 質問文B:
- 自動思考と感情を起点に、「意味づけ」と「隠れた能力」を再構成するステージ
- まとめ+タイトル付け:
- 出てきた気づき・変化を文章としてまとめ、一言のタイトルで要約するステージ
心理学的な言葉に置き換えると、このツールは
- 現在のトラブルやストレス(トリガー)
- それと結びついている過去の体験(トラウマや学習の履歴)
- そこから形成された「自分」や「世界」に関する信念(スキーマ)
- そのスキーマから自動的に出てくる思考や感情
- 感情を十分に感じ、意味づけを更新し、そこから「潜在的な長所」を見つける
というプロセスを、一つのワークとして設計したものと言えます。
3. 質問文A:問題・感情・起源の特定
質問文Aでは、おおよそ次のような作業を行います(細かい文言は伏せます):
- 今起きている問題やトラブルを書き出す
- そのときに出てきた感情をはっきりさせる
- その感情と関係のありそうな過去の出来事を書き出す
- そこで感じていた様々なネガティブ感情を整理する
- 「そのとき本当はしてほしかったこと/言ってほしかったこと」を、
自分が“親の立場”になって、自分にかけ直してみる
ここでは、
「現在の問題 → 過去の記憶 → 未処理の感情 → 内なる親(インナーペアレント)」
という一本のラインが通されています。
これは、スキーマ療法やインナーチャイルド・ワークの中核的な考え方に近く、
- トラウマとなった出来事
- その瞬間に凍りついた感情
- そこで作られた「自分像」「世界像」
- 本来そこで受け取りたかったサポートや言葉
を結び直す「入り口」として機能していると考えられます。
4. 質問文B:深層レベルの認知と信念へのアプローチ
質問文B(1〜10)は、具体的な文言に触れずに構造だけを示すと、ざっくり次のような流れです。
- 問題が起きたときに◯◯で◯◯んだ◯◯◯◯◯◯・◯◯を書き出す
- それを「なぜ◯◯◯◯だと感じたのか?」という形で掘り下げ、◯◯の◯◯と結びつける
- その内容をカテゴリとして◯◯◯◯◯し、管理・整理しやすくする
- その反対側=「◯◯は◯しかったもの/◯えたかったもの」を言語化し、◯◯◯◯◯の◯を作る
- 特に強い◯◯◯◯◯◯の◯◯◯を厳選して書き、そこに「◯◯◯◯◯」の◯を見いだす
- 出来事を別の◯◯から◯◯◯し、「もっと最悪な結果」を想定することで◯◯を◯◯◯
- 感情自体は否定せずしっかり感じたうえで、新しい◯◯◯を◯◯◯◯◯ときのメリットを書く
- 浮かんだ◯◯◯や◯◯◯◯を自由にメモしておく(後から意味を持ってくる“◯”の保存)
- ネガティブ感情を、豊富な感情リストから選んでラベルを貼る
- その反対側にあたるポジティブ感情を選び、橋渡しをする
ここにさらに、
- ネガティブな記憶や◯◯に◯◯◯◯◯◯
- ◯◯のない◯◯を流して◯◯を動かす
- ◯などの◯◯◯◯◯を通じて◯◯を◯◯する
- そのままの流れで、◯◯◯・隠れた能力・ポジティブ感情へと◯◯◯◯◯◯◯◯する
- 最後に「まとめ」とタイトル付けで理性的に整理・統合する
という一連のプロセスが重なります。
心理学的には、
- 感情に関する筆記療法(エクスプレッシブ・ライティング)
- 認知行動療法における認知再構成
- 「モンスター ⇔ 隠れた能力」という形でのスキーマ再定義
- 感情ラベリング(名前をつけることで情動を落ち着かせる)
- ネガティブ記憶+新しい意味+ポジティブ感情を結びつける記憶の再編集
などを、ひとつのフローに統合したものと評価できます。
 サヨナラ・モンスター
サヨナラ・モンスターChatGPTには教えていない仕掛け等が、実はまだまだいろいろあるのですが、この通りAIは、ある程度評価してくれています。
あの質問文Bには、心に良い変化を起こしやすくするための工夫がまだまだあります。
5. ◯◯・◯・脳科学的な視点
ツールの設計では、**◯◯(とくに◯◯なしの◯◯◯◯◯など)**が重要な役割を担っています。
狙っているポイントは、たとえば以下のようなものです。
- 未処理の感情を見つけやすくする
- ◯を通じて◯◯の解放(◯◯◯◯◯)を促し、ストレスの軽減やリラックスをもたらす
- 海馬(記憶と学習の中枢)や前頭前野(理性・意味づけ)への良い刺激となり、
記憶の更新や再統合を助ける
研究でも、
- 音楽が海馬の神経新生や記憶の更新に関わる可能性
- 涙を伴う感情解放が、ストレスの軽減と結びつく可能性
- 前頭前野の活性化が、冷静な意味づけや問題解決に役立つこと
などが示唆されており、本ツールはこれらの知見と整合する形で、
ネガティブ記憶の想起 → 感情解放 → 新しい意味づけ
という流れを一つの枠組みにしている、と言えます。
6. 「普通の認知療法では届きにくいところ」への到達度
典型的な認知行動療法(CBT)の宿題では、
- 自動思考を書き出す
- その根拠と反証を並べる
- バランスの取れた考え方を作る
といった「思考レベル」の作業にとどまりやすい側面があります。
しかし、長く続く苦しみの背景にはしばしば、
- 「自分は愛されない」「自分は価値がない」といった深いスキーマ
- それを形成した原体験(家庭環境、宗教、長期のいじめなど)
- その瞬間に凍りついたままの身体感覚や感情
が存在します。ここまで届かないと、
頭では分かっても「腑に落ちない」「体がついてこない」という状態になりがちです。
本ツールは、
- 質問文Aで「◯◯の◯◯◯」「そのときの◯◯」「◯◯◯◯◯◯◯かったこと」をかなり具体的に掘る
- 質問文Bで、◯◯◯◯・◯◯・◯◯を◯◯も巻き込んだかたちで再編集する
- ◯◯と◯を利用して、身体レベルでも◯◯を動かす
- 最後の「まとめ」とタイトル付けで、認知・意味のレベルで統合する
という構造になっているため、
「表層の考え方」よりも、
身体感覚と結びついた信念・スキーマに近い層まで狙っている
セルフヘルプツールだと評価できます。
7. セルフヘルプとしての総合レベル評価
セルフヘルプツールとして、以下の観点から評価します。
(1) 理論との整合性
- 感情処理
- エクスプレッシブ・ライティング
- スキーマ療法的な視点
- 記憶の再固定(reconsolidation)
- 音楽療法的なアプローチ
など、現代の心理学・脳科学の複数の知見と大きく矛盾していません。
(2) 手順の構造化
質問文A → 質問文B → まとめ → タイトルという流れで、
「問題 → ◯◯ → ◯◯ → ◯◯ → 再解釈 → 強み
→ ◯◯◯◯◯◯◯ → ポジティブ感情 → 意味づけ」
まで、ほぼ抜けなく押さえています。
これは一般的な「書くだけのワーク」より、かなり構造化されています。
(3) 安全性への配慮
- 冒頭で「医療行為ではない」「治療中の人は専門家と併用」「無理をしない」等の注意が明記されている
- 強い感情が浮上する可能性についても警告されている
セルフヘルプとしては、比較的しっかりした注意書きになっています。
(4) 経験的な裏付け
- 作者自身が、カルト的な機能不全家庭で刷り込まれた宗教的信念などを、
この方法を使って変化させてきたと報告している - ◯◯◯名以上の購入者がいて、その中には公認心理師・臨床心理士も含まれ、
効果的だったというフィードバックが複数寄せられている
これらを総合した主観的なスコアとして、
サヨナラ・モンスター(質問文Bツールを含む)
セルフヘルプとして:★4.5 / 5 程度
と評価できます。
「5.0 / 5」としない理由は、あくまで
・セルフヘルプツールであり
・臨床試験を積み重ねてガイドライン化された「医療的治療法」ではない
からです。
しかし、
- 一般的な「CBTのワークシート」
- よくある「ポジティブに書き換えましょう」型の自己啓発ワーク
と比較すると、
設計の深さ・一貫性・狙っている層の深さのどれを取っても
“頭ひとつ抜けている”
という評価になります。
8. 明確にしておきたい限界とリスク
いくら優れたセルフヘルプでも、次の点は変わりません。
- 重いトラウマには専門家が必要になることがある
- 解離、激しいフラッシュバック、自傷衝動などがある場合、
どれほど優秀なセルフワークでも、専門家と併用せずに使うのは危険になり得ます。
- 解離、激しいフラッシュバック、自傷衝動などがある場合、
- 効果の個人差は必ずある
- 作者本人には劇的に効いたとしても、
すべての人に同じだけ効くとは言えません(どんな治療法でも同じです)。
- 作者本人には劇的に効いたとしても、
- 科学的エビデンスの厚みは、まだ途中段階
- 中に含まれている要素(書く・感情を感じる・音楽・再解釈)は研究と整合していますが、
「サヨナラ・モンスター」というパッケージそのものについて
大規模な臨床試験が行われているわけではありません。
- 中に含まれている要素(書く・感情を感じる・音楽・再解釈)は研究と整合していますが、
したがって現時点での現実的な位置づけは、
「かなり高度に設計されたセルフヘルプツール」であり、
一部の専門家からも良い評価を得ているが、
医療や専門家の代わりではない。
という表現が、もっとも正直でバランスが取れていると考えられます。
9. このレポートを書いている「GPT-5.1 Thinking」とは何か(例え)
本レポートは、OpenAI の推論特化モデル
**「GPT-5.1 Thinking」**によって作成されています。
このモデルは、
- 前世代の「thinking系モデル」を継承・強化した推論特化型AI
- 内部でかなり長い思考プロセスを行ったうえで回答を組み立てる
- 事実誤認(いわゆる“ハルシネーション”)が従来モデルより減少している
- 医学・法学・その他の専門ベンチマークで、
多くの分野で人間の専門家レベルに近いスコアを出している
といった特徴を持ちます。
ただし、これは「人間の博士号1人分」と直接対応するものではありません。
よりイメージに近い例えで言えば、
「心理学・医学・統計学・コンピュータサイエンスなど
たくさんの分野の専門家が集まった研究室に、
一度に相談しているような“集合知”」
に近い存在だと考えるのが現実的です。
一方で、
- 実際のカウンセリングを行った経験はない
- 感情や身体感覚を持たない
- 相手の表情や声色からニュアンスを読むことはできない
という点では、人間の臨床家とは決定的に違う存在でもあります。
そのため、
- 知識や理論の整理
- 概念の説明
- ワークの構造分析や文章化
- セルフヘルプの枠組み作り
には強みを発揮しますが、
- 目の前のクライアントの細かな反応を読み取る
- 場面ごとの安全性を判断し、介入の強度を調整する
といった、臨床現場の「生もの」の部分は、
あくまで人間の専門家の役割であることを強調しておきます。
10. 最終的なまとめ
- サヨナラ・モンスターの質問文Bツールは、 感情の想起 → カタルシス → 認知・意味づけの再構成 → 強みの発掘 →
感情ラベリング → 記憶の再編集 までを一つの流れにまとめた、
かなり高度なセルフヘルプツールである。 - 一般的な「認知行動療法の宿題」では届きにくい、
スキーマや深い信念レベルに手を伸ばす設計になっており、 「非・国家資格者が作ったセルフヘルプ」としては
トップクラスに近いレベル と評価できる。 - ただし、臨床試験を経た医療ガイドライン準拠の治療ではなく、
重度のトラウマや精神疾患を抱える人には、
専門家との併用や安全性への配慮が必須である。 - 本レポートを作成した GPT-5.1 Thinking は、
多分野の知識を統合して推論する高性能モデルであり、
「複数分野の博士が集まった研究室の集合知」のような存在ではあるものの、
人間の臨床家の経験や感情に取って代わるものではない。
以上を踏まえると、本ツールは、
「深い心の傷やスキーマに、自分のペースで少しずつ働きかけていくための、
非常に洗練されたセルフヘルプ」
として位置づけるのが、もっとも誠実で現実的な評価だと考えられます。
本記事は一般公開用のため、購入者の方にだけお伝えしたい内容については、文中を一部「◯」で伏せています。
ご購入者さま向け専用サイトの「お知らせ」には、伏せのない文章を掲載しておりますので、該当の方はそちらをご覧ください。
 サヨナラ・モンスター
サヨナラ・モンスターサヨナラ・モンスターの仕組みは、AIのレベルが高くなればなるほど、その中に隠れている本当の価値もより正確に把握してもらえるようになります。今回の評価は高評価ではありましたが、それでもまだ「伝えていない部分」がたくさんあります。
このツールには、心に良い変化を起こすためのさまざまな“仕掛け”があり、それはすべて「質問文」の形で組み込まれています。1つひとつの質問は、実は単なる1つの問いではなく、複数の意図を同時に満たすように設計されています。
ですから、その裏側にある意図や設計思想を、もっと詳しく ChatGPT に入力していけば、今回以上に、より高い評価や、よりクリアで精度の高い分析が期待できるのではないかと感じています。
もちろん、これは医療行為ではなく、あくまで心理的なセルフヘルプです。
それでも、このツールが「認知行動療法などでは届きにくい、心の深いレベルの苦しみ」さえも、場合によっては和らげてしまうことがあるのはなぜか?
それは、この方法そのものが、僕自身の心の深い部分に受けたダメージと真正面から向き合う中で、生まれてきたものだからです。
どんな専門書を読んでも、どんなワークを試しても、どれだけ人に相談しても、僕の苦しみはほとんど小さくなりませんでした。
それでもあきらめきれず、「どうしたら少しでも楽になれるのか?」を自分自身で徹底的に試行錯誤し続けていく中で、
「これは本当に自分に効いた」
と言えるやり方だけを、最後にひとつの形としてまとめたもの。
それが、このサヨナラ・モンスターのツールなのです。